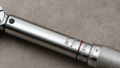「1寸って、何センチか分かりますか?」
そう聞かれて即答できた人は…すでにちょっとマニアかもしれません(笑)。
多くのDIY初心者やリノベに挑戦しようとする人にとって、「寸?尺?それってまだ使うの?」というのが正直なところでしょう。
実はこの「寸」「尺」「間(けん)」という単位、日本の建築や道具づくりの現場ではいまだに現役。ホームセンターの木材コーナーでも、「3尺」「6尺」なんて表記を見かけたりします。
でも、「1尺が何センチか分からないまま作業していた」なんて話もよくありますし、そもそもメートル法で慣れてきた私たちにはピンと来づらいですよね。
この記事では、そんな「寸・尺って何?」「なぜ今も使うの?」という疑問にしっかり答えながら、初心者にもわかりやすく、時にはちょっと笑いも交えて解説していきます。
最後にはDIYで役立つ換算表や、古い寸法図面の読み解き方まで紹介するので、読み終わる頃には「寸尺こわくないぞ」と感じてもらえるはずです!
🪵 そもそも「寸」「尺」「間」って何?
メートルじゃダメなの?日本の伝統的な長さ単位
「長さって、全部メートルでよくない?」
たしかにそう思うのが普通です。だって日本はメートル法の国。学校でも「cm」「mm」「m」しか習わなかったし、スマホの定規アプリだってミリ単位。
でも、いざホームセンターの木材売り場に行ってみると、こんな表記を見かけませんか?
- 「3尺材」「6尺板」
- 「1間(けん)」の棚板
- 畳1枚=1畳(1間×半間)
なんだか昔の時代劇に出てきそうな単位たち。でも、これらは今でも現場でバリバリ使われている”実用寸法”なんです。
1寸・1尺は何センチ?すぐ使える換算表つき
| 単位 | 長さ(mm) | 長さ(cm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1寸 | 約30.3mm | 約3.03cm | 親指の“長さ”が基準 |
| 1尺 | 約303mm | 約30.3cm | 1尺=10寸 |
| 1間 | 約1,818mm | 約181.8cm | 1間=6尺 |
| 1丈 | 約3,030mm | 約303cm | 1丈=10尺 |
※基準は建築用の「曲尺(かねじゃく)」です。
🗣【プチ雑学】
「尺」にはいくつか種類があり、「曲尺=建築用(30.3cm)」「鯨尺=和裁用(約38cm)」などが存在します。
「1寸って約3cm」と覚えておけば、小さな木材や部品の長さも感覚で掴めるようになります。「10寸で1尺」「6尺で1間」という構造も、ちょっと古風だけど合理的。
そして…この構造が、今でも現場で支持される理由につながってくるんです。
🧱 なぜ今でも大工さんは「寸法」を使うのか?
建築にぴったりな“モジュール”としての便利さ
寸・尺・間(けん)がいまだに使われる最大の理由は、「建築に最適化されたモジュール寸法」だからなんです。
特にポイントになるのが「1間=6尺=約182cm」という基本寸法。
これ、実はすごく絶妙なサイズ感なんです。
- 1間(けん)=6尺=1820mm(約182cm)
- 半間(はんげん)=3尺=910mm(約91cm)
このサイズ感が、畳・柱・棚・壁の設計にちょうどよくフィット。ベニヤ板や石膏ボードなど、現在の建材もこのサイズが基本です。
なんで“6尺=1間”?10尺じゃないの?
普通に考えると「10尺=1間」の方がキリがいいですよね。でも、実際には「6尺で1間」。
これには実用性と生活空間のちょうど良さが関係しています。
1尺=約30.3cmなので、6尺=約182cm。
このサイズ、実は日本人の平均身長+αくらいで、**「人が寝転べる長さ」**としてぴったり。
しかもこの1間(182cm)を基準に、畳のサイズ・天井の高さ・柱の間隔などがすべて設計されているんです。
昔の家に入ったとき、「なんか落ち着くな〜」と感じるのは、この間(ま)の感覚が身体に合ってるからかもしれません。
さらに、6という数字は偶数で割りやすいのも大きなポイント。
1間を半分にすれば3尺(約91cm)で、これがよくある柱の間隔=半間。
「1間・半間・1/3間」など、細かく分けやすいので、現場での設計・施工の効率がバツグンなんです。
🗣【小ネタ】
昔の大工は「一間に布団が一枚ちょうど入る」と覚えたそうです。
つまり、布団のサイズ感=間のサイズなんですね。理にかなってる!
📜 寸・尺の起源はいつから?
「寸・尺・間」などの尺貫法(しゃっかんほう)は、なんと弥生時代〜古墳時代に原型があったとも言われています。
ただし、今のように“1尺=約30.3cm”とキッチリ決まったのはもう少し後の話で、基準が整えられたのは奈良時代以降、律令制の時代です。
当時の日本は中国(唐)の文化を取り入れており、「尺」や「寸」などの単位も、唐の制度をモデルにしています。
さらに江戸時代になると、商業や建築が発展したことで、全国的に「曲尺(かねじゃく)」が建築・木工用の基準として定着していきます。
つまり、
🟨 ルーツ → 中国の制度(周・秦・漢)
🟩 日本での標準化 → 奈良時代以降
🟥 現場への普及 → 江戸時代から本格化
という流れです。
🤔「一間=182cm」は昔の人にとって大きすぎたのでは?
まさにそこ!鋭い指摘です。
たしかに江戸時代の平均身長は男性で約155〜160cm前後とされており、現代人よりずっと小柄でした。
なのに「1間=182cm」って、布団を敷いても余るじゃん!って感じますよね。
実はこれ、身長にぴったり合わせたわけではないんです。
この「間(けん)」のサイズは、生活空間としてのちょうど良さに基づいています。
- 布団を敷いて寝られる
- 2人すれ違える幅感
- 畳2枚分で1坪の面積になる
- 柱の間隔を等間隔にできる
つまり、人のサイズに合わせたというよりは、建物を合理的に構成するために選ばれたサイズなんですね。
🗣【余談ですが…】
平安〜江戸の頃の「一丈(いちじょう)」=10尺(約3m)が、ちょうど“背の高い武士の身長”とされていたそうです。
つまり、1丈=「でかい人ひとり分」くらいの感覚だったとか。
🏯 寸・尺の起源をたどる小話
古代中国から伝わった“身体基準”の単位
「寸」や「尺」という単位、じつはそのルーツをたどると、人間の身体のパーツに行き着きます。
- 1寸=親指の幅くらい
- 1尺=親指と人差し指を広げたときの両指先間の長さが由来(約15cm × 2=約30cm)。
- 1間=両手を左右にいっぱい広げた長さ(両手を広げた“間”)
つまり、定規なんてない時代には、自分の体がメジャーだったんですね。
これが、中国(殷〜周〜秦〜漢の時代)において「身体尺」として使われ始め、やがて制度として整備されていきました。
そして日本に伝わったのが、弥生〜古墳時代あたり。
正式に国家単位で使われるようになったのは、奈良時代の律令制においてです。
親指の幅って2㎝ぐらいじゃないの?
おおっ、鋭い!これを読んでいるあなた!その通りです!!
「1寸=親指の幅」ってよく言われるんですが、実際には“親指の長さ**”がルーツ”**という説のほうが有力です。
つまり、昔の「身体尺」としての“寸”は👇
🔸 1寸 ≒ 親指の長さ(付け根から先端)
🔸 それが約3cm前後 → 現代の「1寸=約30.3mm」につながる
❌ よくある誤解:「親指の幅が1寸」
実はこれ、語感やイメージが先行した俗説です。
現代人の親指の幅はたしかに1.5〜2cm程度しかないので、「幅が1寸(3.03cm)」だとちょっと無理がある。
一方、「親指の長さ(爪の先まで)」はだいたい3cm前後あるので、こちらのほうがしっくりくるんですよね。
実際に検索をしてみると 一寸は親指の幅 と記載されている情報も多々あるよう・・・
🔍「親指の幅=1寸」と言われるようになった理由(考察)
✅ 1. 現場での“ざっくり目安”として広まった説
- 昔の大工さんや職人のあいだで、「これ何寸くらい?」→「親指くらいだな、1寸くらいか」
- 実際には正確な長さじゃないけど、「指を使って測る文化」が根強かったため、“目安”として定着
- 親指の幅は目で見て、感覚でパッと判断しやすかった
つまり、現場の感覚測定として広まり、定着した俗説というわけです。
✅ 2. イラストや図解で「幅」として描かれた影響
- 教材・雑誌・解説書などで、親指の「幅」に1寸のスケールを当てて描かれたイメージが普及
- 特に“図解で分かる”系の本では、「幅=1寸」と描く方が視覚的にわかりやすかった
このせいで、「あっ、親指の幅が1寸なのね」と誤解されやすくなった。
✅ 3. 会話の中で「指の幅≒1寸」として使われやすかった
- 実際の会話で「それ親指幅くらいだね」→「1寸くらいか〜」
- このようなラフなやりとりが積み重なり、やがて**“親指の幅=1寸”という俗説**に
🧠【まとめると】
「親指の幅=1寸」は、もともと現場での“目分量”や“たとえ話”として使われたラフな表現が、後世に誤って伝わっていったものと考えられます。
日本で独自進化!江戸の大工文化が育てた「曲尺」
日本で建築や木工の現場に「寸・尺」が根づいたのは、なんといっても江戸時代以降。
この時代、大工や職人の数が爆発的に増え、町屋や蔵、長屋などが全国に広がります。
この頃使われ始めたのが、今の建築でも標準になっている「曲尺(かねじゃく)=約30.3cm」です。
なぜこの長さが選ばれたかというと、
- 柱と柱の間を等間隔に取るのに便利
- 間(ま)を美しく整えられる
- 寸法を暗算しやすい(6尺で1間、10寸で1尺)
という作業効率と見た目のバランスが非常に良かったから。
それまで各地でバラバラだった「1尺の長さ」も、この頃には「曲尺=30.3cm」に統一されていきました。
🪚【余談】「かねじゃく」はL字型の差し金(さしがね)に多い規格。
もう一つの「鯨尺(くじらじゃく)」は約38cmで、これは和裁用。
着物職人の世界では「鯨尺こそ本尺」なんて言い方もあります。
👘 なぜ和裁は「鯨尺」?寸法が違う理由とは?
DIYや建築で使われる「尺」は、1尺=約30.3cm(曲尺・かねじゃく)が標準。
ですが、**着物づくり(和裁)の世界では、これとは異なる“鯨尺(くじらじゃく)”**という単位が使われています。
🔸 鯨尺とは?どのくらい違うの?
鯨尺は、1尺あたり約37.9cm。
つまり、建築用の曲尺(30.3cm)と比べて、7〜8cmも長いんです。
| 尺の種類 | 長さ(cm) | 用途 |
|---|---|---|
| 曲尺(かねじゃく) | 約30.3cm | 建築・木工・DIYなど |
| 鯨尺(くじらじゃく) | 約37.9cm | 和裁・着物仕立て用 |
🔸 なぜ着物には“長めの鯨尺”を使うのか?
これは大きく分けて、2つの理由があります。
✅ 1. 布地の「反物(たんもの)」に合わせた設計だから
着物に使われる反物は、幅や長さに独自の規格があり、これに合わせて寸法を決める必要がありました。
反物1反の長さが13〜15m前後あり、それを適度な割合で分けたのが鯨尺の1尺。
つまり、布地の都合に合わせて発展した単位なんです。
✅ 2. 和服文化は“身体寸法”ではなく“布の使い方”が基準
洋服は「体のサイズ」に合わせて立体的に縫いますが、
和服は「布をどう折って・巻いて・重ねるか」という考え方。
そのため、布幅・布長に最適化された寸法=鯨尺が使いやすかったんですね。
🧠【豆知識】
鯨尺の“鯨”は、文字通り「鯨のヒゲ」を使った定規があったからとも言われています。
軽くてしなる“ヒゲ尺”は、布地の上でも扱いやすく、和裁には最適だったそうですよ!
🔸 鯨尺を知らないと起こる“あるあるミス”
ホームセンターで「1尺3寸」と表示された木材を見て、
「約49cmくらいかな〜」と鯨尺で計算すると、実際は約39cmという大きなズレに!
DIYやリノベの現場では「曲尺(建築用)」が基本。
和裁や着物の寸法だけが「鯨尺」なので、場面に応じて尺の種類を意識することが大切です。
🧚♂️ 一寸法師ってどのくらい小さいの?
一寸法師=1寸=約3cm。つまり親指サイズ!
- 針の刀を持って旅に出る
- 小さくても一人前の“法師”
- 「一寸」=ちゃんと“測れる”存在
📏 寸・尺はただの単位じゃなく、「人のスケール感」を表す文化でもあるんです。
🛠 DIYでどう使う?尺モジュールの活かし方
910mm=1間の半分の秘密
DIY建材の多くが「尺モジュール」基準。
- 1間=1820mm
- 半間=910mm
ベニヤ板・石膏ボード・棚板などもこのサイズ。これを基準にすると、材料のカットが最小限で済む!
古い図面や材料に出てくる寸法の読み方
| 表記 | 換算 | 備考 |
|---|---|---|
| 2間 | 3640mm | 壁の横幅 |
| 3尺 | 909mm | 半間に近い |
| 1尺5寸 | 約454.5mm | 床高の目安など |
リノベや古民家DIYではよく出てくる。これが読めれば一人前!
メートル派にも便利!換算アプリ・早見表のすすめ
スマホアプリや換算表があるから大丈夫。
- 尺貫法長さ単位変換換算(アプリ)
- 寸尺印刷用早見表 (PDFファイル)
Amazonで買えるおすすめ曲尺(かねじゃく)、寸尺定規など
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 竹製ものさし かね1尺 71897
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 曲尺小型 平 ステン 30×15cm 裏面角目 12114
これ普通の㎝です。
新潟精機 SK 日本製 カーペンターミニ 快段目盛 15cm CM-15KD
🧭 まとめ|「寸尺文化」は古いようで実は理にかなっている
- 建築にピッタリなモジュール
- 材料と設計がシンプルに
- DIYでも使いやすい
- 古い図面が読めるようになる
覚え方と活用シーンまとめ
| 単位 | 覚え方 | 長さ |
|---|---|---|
| 寸 | 親指の長さ | 約3cm |
| 尺 | 定規1本 | 約30cm |
| 半間 | ベニヤ板の幅 | 約91cm |
| 1間 | ベニヤ板の長さ | 約182cm |
🧰 寸尺って、古くさそうで、実はすごく“使える”ヤツでした。
ちょっとした雑学や知識として持っておくだけでも、DIYがもっと楽しく、快適になりますよ!