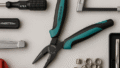DIYをしていると、思わぬトラブルに出くわすことがあります。
例えば——「古い棚を解体しようとしたら、釘が途中で折れて抜けない」「サビだらけのボルトが固着してびくともしない」。
そんな時、多くの初心者はペンチで必死に引っこ抜こうとしたり、ノコギリで切ろうとしたりします。ところが、力任せにやると刃が欠けたり、手をケガしたりする危険があるんです。
実は、こうした場面をスパッと解決してくれる工具が クリッパー。
硬い釘やボルトを切断するために作られた専用の工具で、ペンチやニッパーでは太刀打ちできない相手も、驚くほど簡単に処理できるんです。
もちろん、状況によっては「ネジ外しビットで回す」「ペンチで引き抜く」といった方法も有効です。ですが、どうしても外れないときの“最後の切り札”として、クリッパーはDIY初心者の強い味方になります。
この記事では、折れた釘やボルトに困ったときに役立つクリッパーの基礎知識から、種類・選び方・安全な使い方まで、やさしく丁寧に解説していきます。
折れた釘やボルト、どう処理する?
まずは「抜く」「外す」方法もある
DIYを始めたばかりの人にとって、釘やボルトが折れたり錆びついて動かなくなるのは、とてもやっかいな問題です。
「とにかくどうにかしたい!」と焦ってしまいますが、いきなり切断を考える必要はありません。
まず試したいのは、“抜く”という方法です。
例えば釘なら、ペンチやバールを使って引っこ抜ける場合があります。釘の頭が少しでも出ているなら、そこに工具を引っかけてテコの原理で持ち上げれば、意外とスッと抜けることもあります。
また、錆びて回らなくなったボルトなら、ネジ外しビットや潤滑剤を使うことで外れることもあります。
電動ドリルに専用のビットを取り付け、逆回転でゆっくり回すと「カチッ」と動き出す瞬間が訪れることも少なくありません。
それでも無理なら「切る」方法
ただし、どうしても動かないもの、頭が完全に折れて掴めないものもあります。
そんなとき、無理に力を入れると工具を壊したり、手をケガしてしまう危険があるんです。
そこで登場するのが クリッパー。
硬い金属を切断するために作られた専用工具で、釘やボルトを「もう外せない」と諦めかけた状況でも、スパッと切断して処理できます。
クリッパーを知っているかどうかで、DIYの作業効率も安全性も大きく変わってくるんです。
クリッパーとは?
ニッパーやペンチとの違い
DIY初心者の多くは、まず「ニッパー」や「ペンチ」で何とかしようとします。細い電線ややわらかい針金であれば、それでも対応できることはあります。
しかし、折れた釘や錆びたボルトといった「硬くて太い金属」になると、ニッパーやペンチでは歯が立ちません。刃が欠けたり、手を痛めてしまう危険性もあります。
そこで登場するのが クリッパーです。
クリッパーは、金属の切断に特化した工具。刃の部分が分厚く、テコの原理を最大限に使える構造になっているため、太く硬い釘やボルトでも人の力で切断できるのです。
クリッパーが得意とする「硬い金属の切断」
クリッパーは、単純に「強いハサミ」ではありません。
通常のニッパーは「電線や細い金属線」をカットするのに適していますが、クリッパーはもっと硬い対象物を「押し潰すように」切断するのが特徴です。
例えば、
- 折れた釘の先端を切ってツラに合わせたい
- 錆びて動かないボルトを短くして処理したい
- 小さなチェーンや南京錠を切断したい
こういった場面で威力を発揮します。
つまり、クリッパーは「抜けない・回らない・外れない」といった金属トラブルを解決する、頼れる相棒なんです。
クリッパーの種類
クリッパーといっても、切断する対象によっていくつか種類があります。初心者が混乱しやすい部分なので、まずは代表的なタイプを整理しておきましょう。
- 小型クリッパー(ワイヤークリッパー)
👉 電線や針金、細めの釘の切断に向いています。軽くて扱いやすく、DIY初心者が最初に手に取るならこのタイプ。 - 中型クリッパー(ケーブル・ボルト対応)
👉 少し太めの釘やボルト、小さなチェーンなどを切るときに便利。家庭用DIYならこのサイズが最もバランスが良いです。 - 大型クリッパー(ボルトクリッパー)
👉 錆びたボルトや鉄筋、南京錠の切断まで可能なパワフルタイプ。長いアームでテコの原理を効かせるため、見た目は少し物々しいですが、その切断力は圧倒的です。DIY初心者が最初から買う必要はありませんが、知識として知っておくと安心です。
こうして種類を把握しておくと、「何を切りたいか」によって選ぶべきクリッパーが自然と見えてきます。
クリッパーで切断できるもの
折れた釘(細め〜中くらい)
DIYの作業中に釘が途中で折れてしまうこと、よくありますよね。頭がなくなってしまった釘はペンチで掴めないし、抜こうとしてもビクともしない。そんな時に役立つのがクリッパーです。
細めの釘なら小型クリッパー、中くらいの釘なら中型クリッパーで対応できます。刃先を釘にしっかり当て、テコの原理で力をかければ、見た目以上に簡単にスパッと切断できます。
古い・錆びたボルト
家具や金具の解体で一番困るのが、錆びついて固着したボルト。レンチで回しても動かず、潤滑剤を吹きかけてもダメな場合は、無理に力をかけるとネジ穴を潰したり工具を壊したりしてしまいます。
そんな時は「切る」という選択が正解。中型〜大型のクリッパーを使えば、錆びて動かないボルトも短く切り落とすことができます。無理に外そうとするより安全で効率的です。
チェーンや小さな金具
庭や倉庫で使う細いチェーンや、家具を固定している金具も、クリッパーで切断可能です。
特に中型クリッパーがあれば、DIYで使うレベルのチェーンや金具なら十分対応できます。南京錠のような頑丈なものは大型クリッパーが必要ですが、家庭DIYでは中型で事足りることが多いです。
結束バンドやホースなどのプラスチック類
意外な使い道として、結束バンド(インシュロック)を外すときにも便利です。カッターやハサミでも切れますが、滑って手をケガする危険があります。その点、クリッパーなら安全にカット可能。
また、やわらかめのホースや樹脂パーツも切れるので、DIYだけでなく日常のちょっとした場面でも役立ちます。
初心者におすすめのクリッパー種類
小型クリッパー(軽作業向け)
DIY初心者がまず手に取りやすいのが、この小型クリッパーです。サイズはペンチやニッパーより少し大きい程度で、片手でも扱いやすいのが特徴。
電線や細い釘、針金を切るのに最適で、軽作業が中心の方にはこれで十分です。
値段も比較的安く、ホームセンターやネットショップでも気軽に購入できるため、「とりあえず1本欲しい」という人におすすめです。
中型クリッパー(家庭DIY向け)
釘やボルトを相手にすることが多いなら、中型クリッパーが心強い相棒になります。
長さは30〜45cmほどあり、両手でしっかり握って使うためテコの原理が効きやすく、折れた釘や錆びたボルトも安定して切断可能です。
「小型だと力が足りない…」と感じたら、このサイズを選ぶと失敗が減ります。家庭DIYでは最もバランスが良く、万能タイプといえるでしょう。
大型ボルトクリッパー(知識として紹介)
本格的な作業や、頑丈なチェーン・太いボルトの切断に使われるのが大型クリッパーです。
長さ60cm以上で、両腕を使ってぐっと押し込むことで鉄のチェーンや南京錠さえ切断できます。
ただし、DIY初心者がいきなり購入する必要はありません。持っていると収納場所を取るうえ、普段の作業で使う機会は少なめです。
「世の中にはこんな強力なタイプもある」と知っておくだけでも、クリッパーに対する理解が深まります。
クリッパーの使い方とコツ
正しい姿勢と力のかけ方
クリッパーは「テコの原理」を活かして硬い金属を切る工具です。コツを知って使えば、見た目よりずっと少ない力でスパッと切断できます。
まず姿勢ですが、立った状態で腰の高さくらいの作業台に対象物を置くと安定します。床で切ろうとすると体重をかけにくく、バランスを崩して危険です。
刃の当て方はとても大事で、対象物を刃の奥にしっかり挟み込み、ハンドルを対象に対して垂直に構えること。斜めに当てると刃が滑って思わぬ方向に飛んでしまうことがあります。
握り方は、両手でグリップをしっかり掴み、肘を軽く曲げた状態から体重をかけるように押し込むイメージ。腕の力だけでなく、体全体の重みを使うと楽に切れます。
小型クリッパーなら片手でも扱えますが、釘やボルトの切断では反動もあるため、できるだけ両手で操作するのが安全です。切る瞬間に「カチン!」と一気に力が抜けるので、手元がぶれないようにしっかり構えておきましょう。
切断時に飛ぶ破片への注意
クリッパーで釘やボルトを切断するときに一番注意したいのが、切れ端が飛ぶ危険性です。
金属は切った瞬間に大きな反発力がかかるため、「パチン!」と音を立てて予想以上のスピードで飛んでいきます。まるで小さな弾丸のように勢いがあるので、目や顔に当たれば大ケガにつながる恐れがあります。
実際、作業中に「小さなボルトの切れ端が飛んで壁に当たった」というケースも珍しくありません。運悪く人に当たれば、目に入って失明の危険さえあるのです。
安全に作業するための具体的な工夫としては:
- 対象物を作業台の上で安定させる
手に持ったまま切ると、切断時の反動で破片がどこに飛ぶか予測できません。必ず机や万力に固定してから切りましょう。 - 切断方向を意識する
刃を当てる向きによって、破片が飛ぶ方向もある程度決まります。人やガラス、壊れやすいものがある方向を避けて刃を構えることが大切です。 - 作業スペースを片付けておく
周囲に物が散らかっていると、破片が跳ね返って思わぬ方向に飛ぶことがあります。床や机の上を片付けておくと安心です。 - ゴーグルと手袋を必ず着用
破片が目に飛び込むのを防ぐには保護メガネが必須。手袋は切れ端で手を切るのを防いでくれます。
ちょっとした不注意で「小さな金属片」が凶器になることを覚えておきましょう。クリッパーを安全に使うためには、この“飛ぶ破片”への備えが欠かせません。
保護具(ゴーグル・手袋)の重要性
クリッパーを使うときに忘れてはいけないのが、目と手を守る保護具です。
釘やボルトを切ると、小さな金属片が弾かれるように飛び散ります。その速度は想像以上で、もし目に当たれば失明の危険すらあります。だからこそ、ゴーグルや保護メガネは必須。普通のメガネでもある程度は防げますが、隙間から破片が入り込むことがあるので、できればDIY用のゴーグルを用意しましょう。
次に手袋です。釘やボルトの切れ端は鋭利で、素手で触ると簡単に切れてしまいます。作業中もハンドルが滑ったり、刃先に指が触れたりする可能性があるので、手袋をしておくと安心です。
ただし注意点もあります。布製のゆるい軍手はNG。繊維が刃に巻き込まれる危険があるため、DIYではフィット感のある作業用グローブ(合皮やゴム素材など)が適しています。
さらに、作業する場所によっては耳栓や長袖の服も役立ちます。金属片が体に当たると小さな傷ができたり、服に引っかかることもあるからです。
「ちょっとした作業だから大丈夫」と思って油断した瞬間に事故は起こります。保護具は少し面倒でも、着けることで安心してクリッパーを使えるようになります。安全に作業を楽しむための、最低限の準備だと覚えておきましょう。
ちょっとしたコツ
基本の姿勢や力のかけ方を押さえたうえで、さらに覚えておくと便利な“小ワザ”があります。
まずは**「対象を固定する」こと**。万力やクランプで釘やボルトを固定してから切ると、刃が安定して無駄な力を使わずに済みます。手で持ちながら切ろうとすると、切断の反動で手元がぶれて危険です。
次に、力のかけ方のタイミング。いきなり全力で押し込むのではなく、最初に軽く「カチッ」と刃を食い込ませてから、一気に体重を乗せると切断がスムーズ。刃の滑りや対象の変形を防げます。
さらに、対象の太さと硬さを見極める目を持つことも大切です。「これはちょっと無理そうだな」と感じたら、迷わずワンサイズ上のクリッパーに切り替えましょう。無理に小型で切ろうとすると、工具を壊すリスクがあります。
こうした小さな工夫を加えることで、クリッパーは「ただの硬いものを切る道具」から「安心して使える相棒」へと変わっていきます。
失敗しないクリッパーの選び方
切断対象の「太さ」と「硬さ」で選ぶ
クリッパーを選ぶときに最も大事なのは、「何を切るのか」=太さと硬さです。
これを間違えると「全然切れない」「刃が欠けた」という失敗につながります。
以下の表にまとめたので、対象ごとに目安をチェックしてみてください👇
| 切断対象 | 太さの目安 | 硬さの目安 | 適したクリッパー |
|---|---|---|---|
| 電線・針金 | 〜3mm程度 | やわらかめ(金属線・銅線など) | 小型クリッパー |
| 折れた釘(細め) | 〜4mm程度 | 普通(鉄釘) | 小型〜中型クリッパー |
| 錆びたボルト | 5〜8mm程度 | 硬い(鉄・ステンレス) | 中型クリッパー |
| 家具や建材の太めのボルト | 8〜12mm程度 | 硬い(強度が高い金属) | 中型〜大型クリッパー |
| チェーンや南京錠 | 10mm以上 | 非常に硬い(焼き入れ鋼など) | 大型クリッパー |
👉 ポイントは、「細いものを無理に小型で切ろうとしない」こと。対象が太い・硬いと感じたら、迷わずワンサイズ上を選ぶのが失敗しないコツです。
家庭DIYならどのサイズを選ぶ?
初心者が「折れた釘や錆びたボルト」を処理するなら、30〜45cmほどの中型クリッパーが最も使いやすいサイズです。
小型(15〜25cm前後)は軽くて扱いやすい反面、釘やボルトを切るには刃が小さく、テコの力も十分に効きません。細い針金や電線程度なら問題ありませんが、「折れた釘を根元からスパッと切りたい」といった場面では力不足を感じやすいでしょう。
一方、大型(60cm以上)は圧倒的な切断力がありますが、重量もあり、普段のDIYではオーバースペックになりがちです。収納場所をとるうえ、片手でサッと使うことができないため、初心者が持つには扱いづらさが目立ちます。
その点、中型クリッパーは「扱いやすさ」と「切断力」のバランスがちょうど良いのが魅力です。両手でしっかり握れば、釘や直径8mm程度までのボルトなら問題なく切断できます。家庭で家具を解体したり、庭の補修作業で釘を処理したりするのにぴったりの一本です。
実際、ホームセンターや通販サイトでも「家庭DIY向け」として紹介されるのは、この30〜45cmクラス。価格帯も3,000〜6,000円程度と手頃で、初心者が最初に購入するなら間違いのない選択です。
| サイズ | おおよその長さ | 切断できる対象 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 15〜25cm | 電線・細い針金・細めの釘 | 軽い・片手で扱いやすい・安価 | 力不足で釘やボルトには不向き |
| 中型 | 30〜45cm | 折れた釘・錆びたボルト(〜8mm程度)・小さなチェーン | 扱いやすさと切断力のバランスが良い・家庭DIYに最適 | 若干重いが、初心者でも問題なし |
| 大型 | 60cm以上 | 太いボルト(10mm以上)・南京錠・鉄筋・硬いチェーン | 圧倒的な切断力・プロ用途に対応 | 重くて大げさ・収納場所を取る・価格が高め |
👉 初心者が最初に買うなら、中型クリッパーを選べば失敗しません。釘やボルトのトラブル解決には十分な性能を発揮してくれます。
価格帯とおすすめモデル
クリッパーはサイズや品質によって価格帯が大きく変わります。安いものは数千円で買えますが、プロ向けの大型タイプになると1万円を超えることもあります。目安を表にまとめるとこんな感じです👇
| サイズ | 価格帯の目安 | 特徴 | 初心者へのおすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 小型(15〜25cm) | 約2,000〜3,000円 | 電線・針金・細い釘向け。軽量で片手操作がしやすい。 | △(軽作業ならOK。釘やボルトには力不足) |
| 中型(30〜45cm) | 約3,000〜6,000円 | 折れた釘・錆びたボルト・小さなチェーンに対応。家庭DIYに最適。 | ◎(最初の一本ならコレ!) |
| 大型(60cm以上) | 約6,000〜12,000円以上 | 太いボルトや南京錠、鉄筋も切断可能。重量あり。 | △(プロ向け。DIY初心者にはオーバースペック) |
初心者が「とりあえず一本持ちたい」と思ったら、3,000〜4,000円前後の中型クリッパーが失敗のない選択です。
この価格帯なら切れ味も十分で、釘やボルトの処理には困りません。
さらに、ホームセンターで購入できる国内メーカー(モノタロウ、トラスコ、KTCなど)なら耐久性も安心。Amazonなどの通販では、実際に購入したユーザーのレビューをチェックすれば「釘がスパッと切れた」「固着ボルトも処理できた」などリアルな情報が参考になります。
もし将来的にバイクや車の整備、あるいは鉄工作業まで視野に入れるなら、ワンランク上の5,000〜6,000円クラスを選んでおくのもアリです。
👉SK11(エスケー11) SPIDER ステンレス刃 ミニクリッパー 約200mm
👉近与(KONYO)SUN UP ボルトクリッパー JIS規格 SBC-350 350mm 本体: 奥行2.5cm 本体: 高さ38.5cm 本体: 幅12cm
👉【三方良し】ボルトクリッパー 多用途 ワイヤーカッター 強力切断 チェーンカッター (600mm)
まとめ|折れた釘・ボルトにはクリッパーが最適
DIYをしていると必ず出会う「抜けない釘」「錆びて回らないボルト」。ペンチで引っ張ってもダメ、ノコギリで切ろうとしても時間ばかりかかって危険…。そんな場面で強い味方になるのがクリッパーです。
もちろん、状況によっては「ネジ外しビットで回す」「ペンチで引っこ抜く」といった方法が有効な場合もあります。でも、どうにもならないときの“最後の切り札”として、クリッパーを持っておけば安心。
中でも30〜45cmクラスの中型クリッパーは、折れた釘や錆びたボルトを処理するのにちょうど良いバランス。値段も3,000円前後から手に入り、家庭DIYならこれ一本でほとんどのシーンに対応できます。
安全に使うためには、正しい姿勢や刃の当て方を意識し、ゴーグルや手袋などの保護具をしっかり身につけることが大切です。ほんの少しの注意で、作業効率と安全性が大きく変わります。
「もうどうにもならない」と投げ出したくなる折れた釘やボルトも、クリッパーがあれば解決できる。そんな頼もしい相棒を、ぜひあなたの工具箱に加えてみてください。