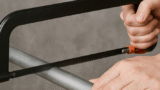「ディスクグラインダーって気になるけど、ちょっと怖そう…」
バイクのカスタムやDIYが趣味の人なら、一度はこう思ったことがあるのではないでしょうか。金属を切断したり、サビを削ったり、パーツを磨いたり――使いこなせれば心強い存在。でも「火花が出る」「うるさそう」「ケガしそう」といったイメージが先行して、なかなか手が出ないという人も少なくないはずです。
特に戸惑いやすいのが、「砥石(といし)」の存在です。
そもそも読み方すら自信がない…という声もよく聞きますし、「え? 包丁を研ぐアレのこと?」と思った人も多いでしょう。確かに「砥石」は、包丁やナイフを研ぐための“石”のことも指します。でも、ディスクグラインダーで使う砥石はまったく別物。円盤状になっており、回転の力で「削る」「切る」「磨く」などの作業を一気にこなすための“専用アタッチメント”なんです。
そしてこの砥石にもさまざまな種類があり、用途によって使い分ける必要があります。金属を切るには「切断砥石」、サビを落とすなら「研削砥石」、表面を整えるなら「フラップディスク」や「ワイヤーブラシ」など…知らないと選べない、けれど知ればとても便利。そんな存在です。
実は筆者自身も、最初は火花にビビっていました。「バチッ」と火が飛ぶたび、思わず体が引けてしまったのをよく覚えています。でも、一度使ってみるとそのパワフルさと汎用性に驚き。「あ、これがあれば作業の幅が一気に広がるんだ」と実感しました。
この記事では、そんなディスクグラインダー初心者が感じる不安や疑問にやさしく寄り添いながら、以下のポイントを徹底解説していきます。
- ディスクグラインダーの基礎知識
- 砥石の選び方と違い(包丁用との比較も)
- バイクDIYに活かせる具体的な使い道
- 安全に使うための手順と注意点
- 実際に使ってみた体験談
「ディスクグラインダーって、意外と怖くないかも?」
そう思ってもらえるよう、この記事が最初の一歩の手助けになれば幸いです。
ディスクグラインダーって何?まずは基本から

AC100V ディスクグラインダー
G10SH7
トイシ径100mm
樹脂ボディ
細径Φ56mm
スライドスイッチタイプ
G10SH7 【ディスクサンダー】
読み方は「といし」?まずは名称の基本
ディスクグラインダーは、「サンダー」と呼ばれることもありますが、正式には電動工具のひとつで、「高速回転する円盤状の砥石(といし)」を使って、金属などの硬い素材を削ったり、切ったりするための工具です。
ちなみに「砥石(といし)」という言葉、聞いたことはあっても「包丁を研ぐあの石でしょ?」と誤解されがち。確かにどちらも“摩擦で削る”という意味では同じですが、ディスクグラインダーに装着する砥石は、円盤型で、強力に回転しながら素材に当てて使うもの。用途も構造もまったく異なります。
この砥石は「ディスク」や「カッター」とも呼ばれることがあり、目的別にさまざまな種類があります。だからこそ、「何を使えばいいか?」で迷う人が多いのです。
どんな場面で使うの?用途を具体的にイメージしよう
ディスクグラインダーが活躍するのは、ざっくり言えば「金属の切断・研削・研磨」の場面です。たとえば:
- バイクのフレームを切る(チョッパー化など)
- マフラーの錆を落とす
- ボルトの頭を削って高さを低くする
- 金属プレートのバリ(鋭利な出っ張り)を落とす
- パーツの溶接跡を平らに仕上げる
- 塗装前の表面処理をする
つまり、金属に関わるDIY作業で「ちょっとプロっぽい仕上げをしたい」と思ったときに、ディスクグラインダーは非常に強力な味方になります。
DIYに使える?バイクカスタムに活かせる作業とは
バイクカスタムの現場では、実はディスクグラインダーはかなり頻繁に使われています。筆者が最初に体験したのは、ホンダ・スーパーカブのステップを外して自作のステーを付けたとき。既存のステーのリベットをグラインダーで切断する必要があったのですが、手作業ではどうにもならず、借りたグラインダーで「シュイィィィン!」と削った瞬間、これまでの苦労が一瞬で吹き飛んだような感動を覚えました。
もちろん、音や火花には最初びっくりします。でも、正しい装備と使い方さえ身につければ、その威力はDIYの世界を一気に拡張してくれると実感しました。
おすすめディスクグラインダー!!!
やっぱり安心のハイコーキ!
これ持っておけばほんとに使える!
HiKOKI(ハイコーキ) AC100V ディスクグラインダー G10SH7 トイシ径100mm 樹脂ボディ 細径Φ56mm スライドスイッチタイプ G10SH7 【ディスクサンダー】
まぁ安くてもいいか? って方はこんな安いやつもありますよ!
自分は最初にこんな安物買いましたけど・・・まったく壊れず、現役です!
SENTOOL ディスクグラインダー 100mm コード式 1台で5役 AC100V 600W オフセット砥石(研削用)2枚付属 穴径15mm ベビーサンダー 研磨工具 アングルグラインダー TDG100 (単速)
砥石の種類と選び方|用途に合った選定ポイント
包丁用の砥石とどう違う?用途の根本が違います
まずは多くの人が抱く疑問に正面から答えましょう。「砥石(といし)って包丁研ぐやつでしょ?」――確かにその通り。でも、ディスクグラインダーで使う砥石は、まったく別モノです。
包丁用の砥石は長方形で平ら。水や油を使って、手作業で刃を研ぎ上げるための「手仕上げツール」です。それに対してディスクグラインダーの砥石は、モーターの回転で毎分1万回近くも高速回転し、硬い素材を一気に「削る・切る・磨く」ための消耗型ディスク。刃物を丁寧に仕上げる道具というより、「荒々しく加工する力仕事の相棒」といった存在です。
混同しがちですが、まったく別ジャンルのツールと考えてOKです。
切る?削る?磨く?|砥石の主な種類と特徴
ディスクグラインダー用の砥石は、大きく分けて以下の種類があります。それぞれの特徴と用途を見てみましょう。
① 切断砥石(カットオフホイール)
- 特徴:厚さ1〜2mmと薄く、金属やボルト、鉄パイプなどを「まっすぐ切る」ことに特化
- 用途:フレームの切断、金属パーツの分割など
- 注意点:薄いため割れやすく、斜めから当てると破損の恐れあり
私これを使用しています☆

ディスクグラインダー用切断砥石
鉄工用 5枚 100×2.2×15mm
② 研削砥石(グラインディングホイール)
- 特徴:厚みがあり、砥粒が粗く、素材を「ガリガリ」削る用途に向く
- 用途:溶接跡の除去、バリ取り、錆び落としなど
- 注意点:表面が荒くなるので、仕上げには不向き

③ フラップディスク(ペーパー砥石)
- 特徴:紙ヤスリのような研磨布が扇状に重なった構造
- 用途:表面磨き、サビ取り、塗装前の仕上げ
- 利点:研削力と仕上げのバランスが良く、初心者向け

ディスクグラインダー用 60グリット
研磨ディスク ジルコニアタイプ
ステンレス鋼・鋳鉄・板金用 10枚
④ ワイヤーブラシ(カップ型/ホイール型)
- 特徴:金属製のブラシが回転し、表面をこすり落とす
- 用途:厚いサビ、塗膜、汚れの除去など
- 注意点:硬いブラシほど素材への影響も強くなる

両頭グラインダー用 ワイヤーホイル 150mm
自分に合った砥石の選び方|バイクDIYの場合
バイクカスタムや修理でよくある作業別に、おすすめの砥石をまとめると次のようになります:
| 作業内容 | おすすめ砥石 | 補足 |
|---|---|---|
| 鉄パイプを切断 | 切断砥石(1mm厚) | 無理に曲げず、まっすぐ切ること |
| 溶接跡の除去 | 研削砥石(厚型) | ガリガリ削れるが、深くなりやすい |
| 表面のサビ落とし | フラップディスク or ワイヤーブラシ | 状況に応じて使い分ける |
| アルミや薄板の研磨 | フラップディスク(細目) | 力を入れすぎないように注意 |
ホームセンター?通販?どこで買う?
購入はホームセンター、ネット通販、工具専門店などで可能です。初めての人におすすめなのは以下の2つ:
- ホームセンター:実物が見られる、スタッフに聞ける。スターターに◎
- Amazon・楽天:種類が豊富、レビューで選びやすい。慣れてきたら通販でもOK
特に初めて砥石を買うときは、「自分のグラインダーに対応しているサイズか?」だけは必ず確認しましょう。外径(100mm/125mmなど)や内径(取付穴のサイズ)に注意です。
実際に使ってみた|体験談から学ぶディスクグラインダーの世界
初めての取り付けで戸惑ったこと
最初にディスクグラインダーを手にしたとき、思った以上に戸惑ったのが砥石の取り付け方です。
なんとなく「ネジで固定するんでしょ?」くらいの認識しかなかったのですが、実際には「スピンドルロックボタン」「クランプナット」「フランジ」など、見慣れないパーツにまずびっくり。説明書を何度も読み返しながら、砥石を間違えないように表裏をチェックして、「え、どっちが表?」と一人で格闘していたのを覚えています。
さらに手袋をつけた状態ではナットがうまく回せず、「えいっ」と力を入れたら砥石がぐらついてしまい、最初は不安しかありませんでした。でも、コツがわかると意外と単純で、**“工具を使って締めすぎない”**ことが大切なんですね。締めすぎると砥石が割れる原因にもなるそうで、それを知ってからは締め付けトルクにも気をつけるようになりました。
火花の迫力とその先にある達成感
いざスイッチを入れた瞬間、「ウィィィィン!!」という高音の回転音とともに砥石が回転し、鉄の棒に砥石を当てた瞬間、バチバチッ!と火花が四方に飛び散る…。正直、めちゃくちゃ怖かったです。
「えっ、こんなに火が飛ぶの?家の中でやったら火事になるやん…」と本気で思いました(笑)。
でも、それと同時に、想像以上にスムーズに鉄が切れていく快感。
今まで金ノコでギコギコやっていた作業が、ほんの数秒で終わる。しかも仕上がりがきれい。少しずつ「これは怖い道具じゃなくて、“強力な味方”なんだ」と感覚が変わっていきました。
もちろん火花対策としては、周囲に可燃物を置かない、革手袋や防炎エプロンを着用するなどの準備は必須。火花自体は高温でもすぐに冷めるため、地面で発火することはまずありませんが、「びっくりしないための心構え」はとても大切です。
削る・切る・磨く、3つの作業を試してみて感じたこと
実際に試した作業は、以下の3つです:
- 鉄パイプの切断(切断砥石)
- ボルトの研削(研削砥石)
- 塗装前の下地処理(フラップディスク)
この中で一番インパクトが大きかったのは、やはり**「切る」作業**でした。火花が飛ぶ=切れてる感が強いというのもありますし、結果が見えやすい。
逆に「削る」作業は、じわじわ進む感じで最初は感覚がつかみにくく、力を入れすぎて砥石が減ってしまったり、削りすぎたりしました。最初は軽く当てて、様子を見るのが大切だと痛感。
そして「磨く」作業。これは思ったよりも繊細で、サビや汚れを落としながら、表面を滑らかにするのにとても便利。見た目がきれいになると、やはり気持ちが上がります。
「切る・削る・磨く」――この3つをひとつの工具でこなせる。
それがディスクグラインダーのすごさだと、改めて実感しました。
正しい使い方と安全対策
ディスクの回転方向と「向き」の考え方
ディスクグラインダーには**「回転方向」**があります。
この向きが正しくないと、砥石の性能が十分に発揮されなかったり、危険な事故につながることもあります。
グラインダーのボディには「→」のような矢印が書かれており、それがモーターの回転方向を示しています。砥石にも同じく、方向性があるタイプでは矢印が印刷されていて、これをグラインダー本体と合わせて取り付ける必要があります。
たとえば、切断砥石で鉄パイプを切るとき。回転方向を間違えると、削る力が逃げてしまってなかなか切れないだけでなく、最悪の場合砥石が跳ね返ってくる“キックバック”の原因になります。これはDIYで最も怖い事故の一つです。
だからこそ、「向き」は必ず確認すべきポイント。
砥石が「正しく削る側」で当たるように取り付けましょう。
砥石の交換方法と取り付けの基本手順
砥石(ディスク)の交換は、一見複雑そうに見えますが、やってみると意外とシンプルです。
基本的な手順:
- 必ず電源を抜く/バッテリーを外す
誤作動防止のため、最重要です。 - スピンドルロックボタンを押す
本体側にある「押し込むと軸が固定されるボタン」を押しながら、ディスクを回して止まるポイントを探します。 - クランプナットを外す
付属のスパナでナットをゆるめて外します。反時計回りで回すのが一般的です。 - 砥石を取り外し、新しいものに交換
表裏・回転方向を確認して正しくセット。 - クランプナットで固定し直す
“手締め+最後に軽くスパナで固定”が基本。締めすぎ注意!
砥石は「消耗品」です。使い込むほどに小さくなり、性能も落ちていきます。「なんか削れにくいな…」と思ったら、迷わず交換しましょう。
危険を避けるための安全装備と作業環境
ディスクグラインダーは便利な反面、事故につながるリスクも確実に存在します。だからこそ、安全対策は“やりすぎ”なくらいでちょうどいい。
最低限そろえたい装備は以下の通り:
- 防塵ゴーグル/フルフェイスシールド:飛んでくる火花や破片から目と顔を守る
- 厚手の革手袋:砥石の熱やバリでのケガを防ぐ
- 耳栓/イヤーマフ:作動音は100dBを超えることも。長時間は危険
- 長袖の作業着/エプロン:火花は服にも飛ぶため、肌の露出は避ける
- 防塵マスク:金属粉を吸い込むと喉や肺にダメージあり
また、作業場所の確保も重要です。
火花は飛距離が意外と長く、1m以上先にも届くことがあります。周囲には紙、布、ガソリンなどの可燃物を置かないようにしてください。できれば屋外、または火花の飛散を防ぐシートを設置するのがおすすめです。
よくある失敗と対処法
「全然削れない…」→力の入れすぎが原因かも
ディスクグラインダーを初めて使うと、つい力を入れて押しつけたくなります。
筆者も最初のころは「もっと押しつければ早く削れるはず!」と思い込み、グイグイと押し当てていました。でもそれが逆効果。
ディスクグラインダーは砥石が高速回転する力で素材を削るので、実は「軽く当てる」くらいでちょうどいいんです。力を入れすぎると、砥石の表面が詰まったり、摩擦熱で素材が焦げたり、砥石そのものの寿命を縮めたりしてしまいます。
特に研削砥石やフラップディスクでは、**“撫でるように削る”**感覚がベスト。
「スーッと当てて、あとは砥石の力に任せる」これを意識するだけで、削り心地も仕上がりも一気に変わります。
「砥石が割れた!」→締めすぎや誤使用が原因
ディスクが割れる…これは最も怖い失敗例のひとつです。
たとえ小さな破片でも、数万回転の勢いで飛んでくると、皮膚を切るどころか、顔や目に大ケガを負う危険もあります。
砥石が割れる主な原因は:
- クランプナットの締めすぎ
- 誤った取り付け方(フランジの向きが逆など)
- 本体と砥石サイズが合っていない
- 落下や衝撃でひびが入っていた砥石を使用してしまった
- 用途外の使い方(切断砥石で削るなど)
もし「カタカタ音がする」「回転時に微妙にブレる」など違和感があれば、すぐに使用を中止し、新しい砥石に交換してください。安全第一です。
「作業中に本体がブレる」→持ち方・姿勢・回転方向を見直そう
グラインダーを動かしている最中に本体がブレるというのも、よくある悩みです。
これは主に以下の3つが原因。
- 回転方向に逆らって動かしている
→砥石の回転に対して“逆方向”に押し付けてしまうと、バウンドのような跳ね返りが起きてブレやすくなります。 - 本体の持ち方が安定していない
→片手で持つと振られやすく、力も入りにくい。基本は両手持ち(補助ハンドル付きなら必ず使用) - 作業台や素材が不安定
→切る対象がグラついていたり、足元が滑りやすいと、全体が不安定になります。
ブレると焦ってさらに力を入れてしまい、ケガや破損につながる負のスパイラルに。
一度作業を止めて、「グラインダー本体の保持姿勢」「砥石の回転向き」「対象物の固定」をすべて見直してみてください。
以上のように、ディスクグラインダーは“正しく使えばとても頼れる存在”ですが、“少しの間違いで一気に危険が増す工具”でもあります。
でも、最初にこうした失敗例を知っておけば、怖がらずにうまく付き合うことができるんです。
【体験談】マスクをせずに切断して後悔した話
あるとき、鉄パイプをグラインダーで切断していたのですが、「ちょっとだけだから」とマスクを付けずに作業をしてしまいました。
終わった直後は「よし、終わった」と満足していたものの――数時間後、ふと気づくと鼻の中が真っ黒。ティッシュでかんでも、黒い粉がなかなか取れず、それ以上に気になったのが口の中や鼻に残る“鉄のにおい”。まるで錆びた鉄板を舐めているような、独特の金属臭がずっと取れず、喉の奥にまで残る感じ。
「こんな空気、思いっきり吸ってたのか…」とゾッとしました。
それ以来、どんなに短時間の作業でも、マスクは必ず着けるようにしています。
まとめ|最初の一歩は“怖さ”を超えるところから
ディスクグラインダーは、確かに最初は少し怖い工具です。
火花が飛ぶ。音が大きい。うっかりするとケガのリスクもある。
でも――それと同時に、「作業を何倍もラクに、そしてキレイにしてくれる力」を持った、頼もしいパートナーでもあります。
包丁を研ぐ砥石しか知らなかった頃には想像もつかなかった「回転する円盤のパワー」は、バイクのフレームを切断し、ボルトのバリを取り、マフラーの錆を一掃してくれました。
金ノコや紙ヤスリでは到底たどり着けなかった“作業のスピード感”と“仕上がりの美しさ”に、一度ハマると抜け出せなくなる人も多いでしょう。
かく言う筆者もその一人です。
もちろん、選ぶべき砥石の種類や、正しい向き、取り付け方法、安全装備――覚えることは多いかもしれません。
でも、この記事で紹介したように、ポイントさえ押さえれば、ディスクグラインダーは決して“怖いだけの工具”ではありません。
あなたのDIYがさらに自由で、創造的になるために。
もし今、「ちょっと使ってみようかな」と思ったなら、それが“最初の一歩”です。
怖さを超えた先には、“できることが広がる”楽しさが待っています。
ぜひ、自分に合ったグラインダーと砥石を選んで、最初の一切り、最初のひと削りを楽しんでみてください。
Amazon ディスクグラインダー おススメ
- DayPlus ディスクグラインダー コード式 グラインダー 100mm 900W アングルグラインダー 工具 DIY 研磨工具 オフセット砥石 カーボンブラシ付属 アングルグラインダー 軽量 サイドハンドル 日本語取扱説明書
- 高儀(Takagi) 変速ディスクグラインダー 100mm EARTH MAN DGR-110SCA【過負荷保護機能付き】 サンダー工具 変速ディスクグラインダー ヘビーサンダー グラインダー 雑草ブラシ
- マキタ ディスクグラインダ18V 100mm スライドスイッチ型 バッテリ充電器別売 GA402DZ
- ディスクグラインダー 砥石 一覧リンク